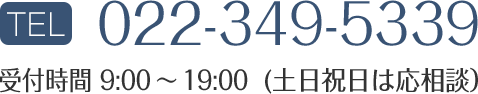相続の流れ
相続順位とは
相続の手続きでは亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産や預貯金などを相続する人(相続人)に移転します。手続きには期限があり、亡くなった日から開始します。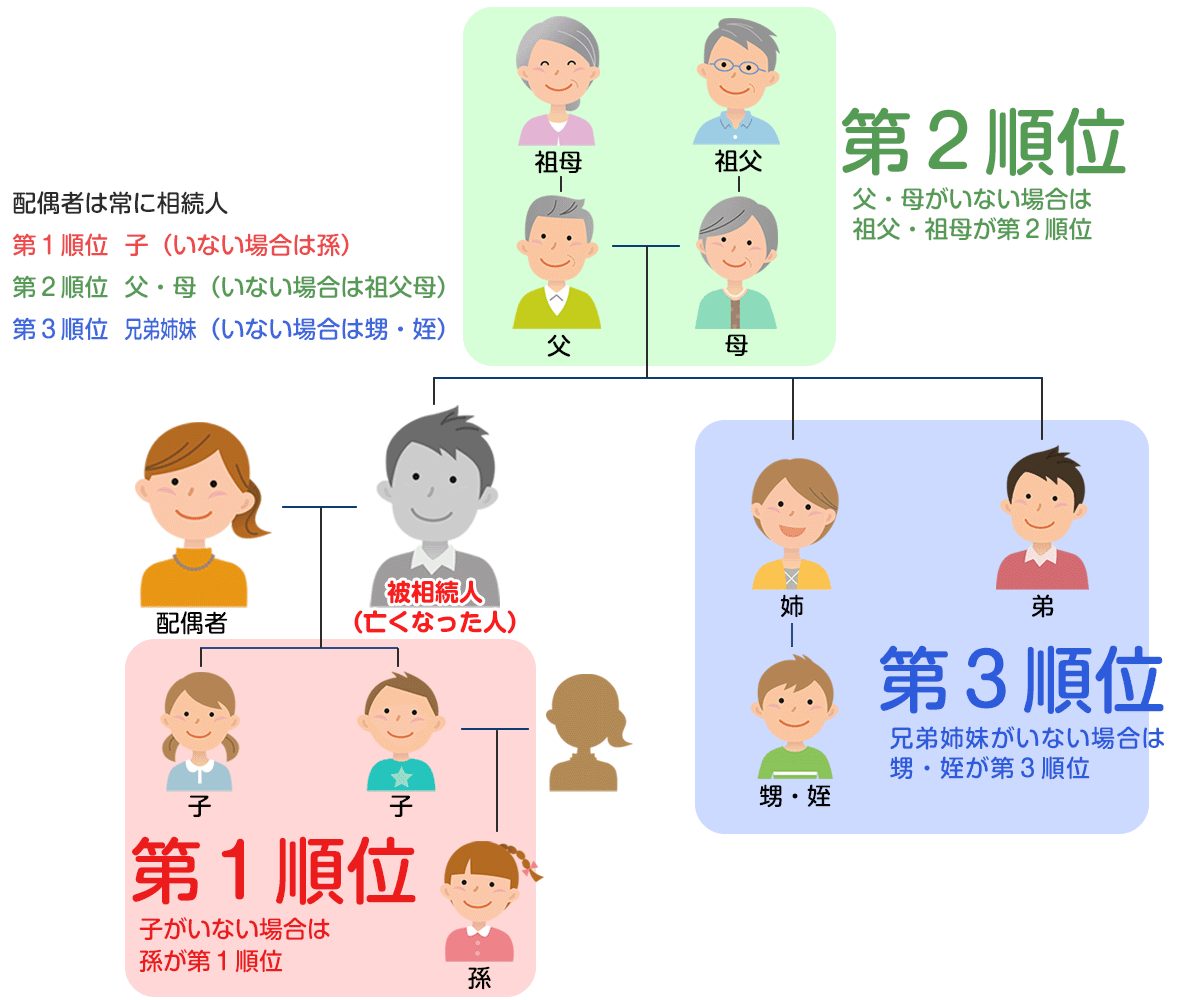
配偶者は必ず相続人になります。
相続の第1順位は子になりますが、子が死亡していない場合は孫が相続人になります。
第1順位が誰もいない場合、第2順位の父・母が相続します。父・母がいない場合は祖父・祖母が相続します。
第2順位が誰もいない場合は第3順位の兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹がいない場合は甥・姪が相続します。
相続手続きの流れ
相続の期限は被相続人が亡くなった当日から開始します。相続するかを決める期限は3カ月以内です。負債などが多く相続放棄をする場合は3カ月以内に決めましょう。
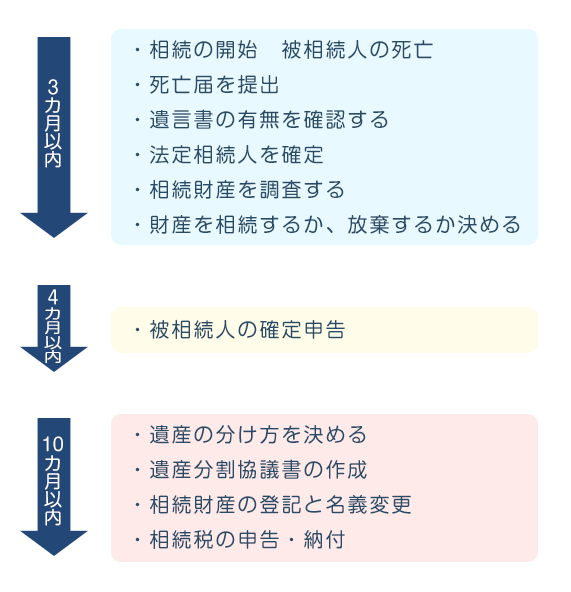
まずは遺言書の有無を確認しましょう
遺言書の有無によって相続手続きはだいぶ変わります。通常、法律により相続財産の分け方が決まりますが、正式な遺言書がある場合は遺言書が優先されます。遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、主にこの3種類があります。すぐに開封せず開封前に必ず検認を行いましょう。(検認は裁判所で遺言書を確認記録する手続きです)
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言書のです。公証人が確認しながら作成するため、無効になる危険性はほとんどありません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は自筆で書く遺言書です。財産目録は署名以外はパソコンでも作成できます。
秘密証書遺言
遺言の内容を遺言者以外に知られることがありません。偽造などの危険性が低くなりますが、家庭裁判所の検認が必要で書類に不備が生じやすいです。
法定相続人を特定する
法定相続人とは民法で定められた相続する権利のある人です。法定相続人になれるのは配偶者、子供、親、兄弟姉妹です。配偶者が優先されます。第1順位の子供、孫が健在の場合は第2順位、第3順位の人は相続人になれません。
法定相続情報証明制度を活用しましょう
法定相続情報証明制度を利用しますと、複数の申請先(法務局、銀行、税務署など)に同時に提出できます。いままでのように各窓口に戸籍書類一式を順番に出す必要がなくなり、戸籍謄本などを何度も取得する手間と費用を減らせます。
認証文つきの法定相続情報一覧図の写しが必要な通数交付されます。相続手続きの負担軽減にご活用ください。
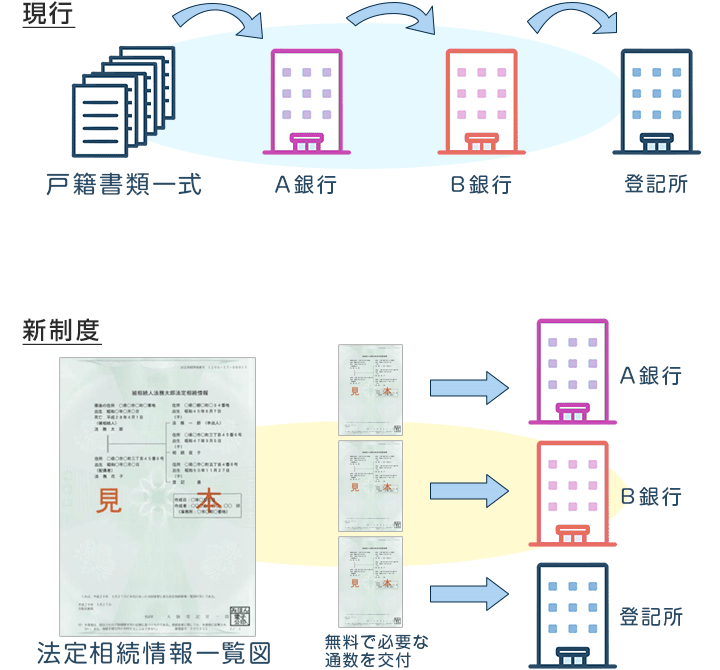
相続財産を調査する
相続財産になるものは不動産、預貯金、株式などはもちろん、仮想通貨や電子マネー、ネットバンクなどインターネット上にだけ存在するため、通帳が存在しないものもあります。また、財産には借金や住宅ローンなどマイナスの財産も含まれます。
相続放棄と限定承認
相続する財産には借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産が多い場合は相続しないということができます。これを相続放棄といいます。また、プラスかマイナスか判断しにくい場合に限定承認という方法もあります。
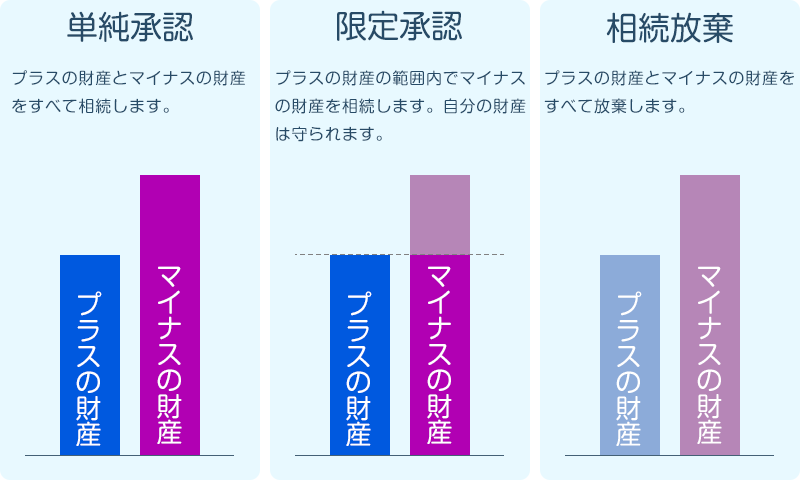
単純承認
プラスの財産とマイナスの財産をすべて相続します。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続します。マイナスの財産も相続しますが自分の財産は守られます。
相続放棄
プラスの財産とマイナスの財産をすべて放棄します。
相続財産の分け方
相続財産が確認できましたら財産をどのように分けるかを決めます。遺言書があれば遺言書が優先されますが、相続人全員で遺産分割協議を行えば、遺言書と違う分け方もできます。財産の分け方には4つの方法があります。
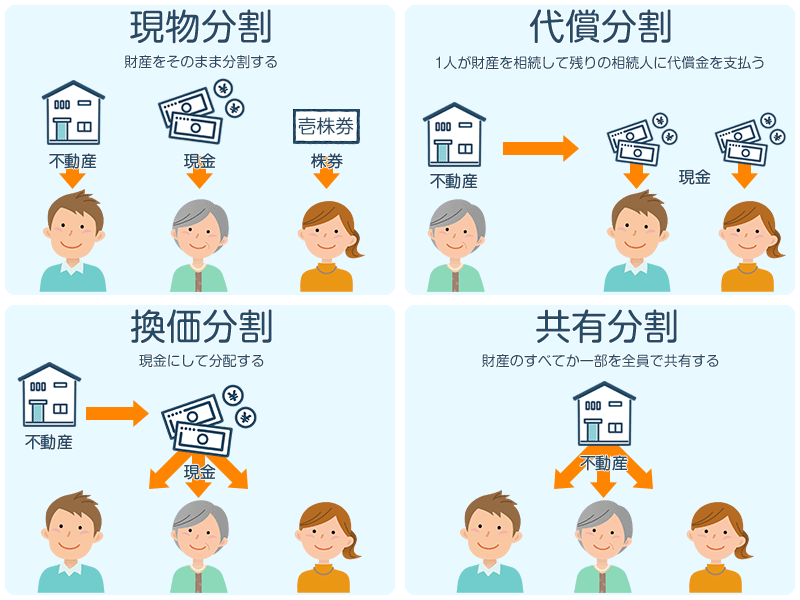
現物分割
財産をそのまま分割する方法を現物分割といいます。手続きは簡単ですが財産を平等に分けることが難しい場合もあります。
代償分割
1人が財産を相続して残りの相続人に代償金を支払う方法を代償分割といいます。相続財産に不動産がある場合などは金銭の支払い能力が必要です。
換価分割
現金にして分配する方法を換価分割といいます。平等に分けられますが不動産の売却に手間がかかることがあります。
共有分割
財産のすべてか一部を全員で共有する方法を共有分割といいます。不動産の共有はのちにトラブルになることがあるので慎重に決めましょう。
遺産分割協議書を作成する
相続財産の分け方を相続人全員で話しあって決めることを遺産分割協議といいます。相続人全員の参加が必須で一部の相続人を排除すると無効となります。協議を始める前に入念に相続人調査を行いましょう。
遺産分割協議が終了したら揉め事が起こらないよう遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名、捺印 (実印) 及び印鑑登録証明書が必要です。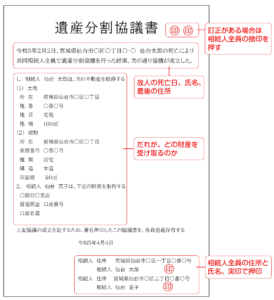
相続財産の登記と名義変更
相続財産に含まれるものは預貯金、株式、不動産、車、船舶、書画、宝石、生命保険、退職金、会員権など金銭的価値があるものです。
預貯金の名義変更
預貯金の相続は、まず口座の名義人が亡くなったことを金融機関に連絡します。口座が凍結されて預金の引出し、口座振替ができなくなります。次に、所定の申請書(相続確認表、相続関係届書など)を入手して預貯金を相続する人が提出します。提出期限は相続開始から10カ月以内です。
必要となる書類は金融機関所定の申請書、戸籍謄本、印鑑証明書、などですが金融機関により異なるので確認しましょう。
株式の名義変更
株式の相続は、証券会社などに所定の書類を提出します。有価証券は解約・換金して分割するか、名義変更をして継承しましょう。提出期限は相続開始から10カ月以内です。
必要となる書類は、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本、などですが遺言書の有無で異なります。金融機関に確認しましょう。
不動産を相続する
不動産の相続方法は遺言書があれば遺言書を優先します。ない場合は遺産分割協議を行って決めます。所有権移転登記の期限はありませんが早めに行いましょう。不動産相続の申請は不動産がある住所を管轄する法務局へ提出します。
仙台法務局 管内法務局一覧:仙台法務局(houmukyoku.moj.go.jp)
提出する際に必要な書類は以下になります。すべて集めるのが大変な場合はご依頼ください。
・遺言書(遺言書が無い場合は遺産分割協議書)
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産相続をする人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の登記事項証明書
不動産登記の申請書様式について:法務局 (houmukyoku.moj.go.jp)
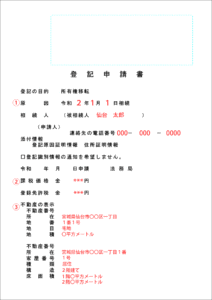
①「原因」「相続人」は被相続人が亡くなった日付です。
② 「課税価格」「登録免許税」は自分で計算するか法務局で確認しましょう。
③ 「不動産の表示」は登記簿謄本などにある不動産番号を記載すれば所在や地積を省略できます。ご不明な点はご相談ください。
相続のよくあるご相談
Q,相続の手続きはいつまでにしたらいいですか?
A,相続の手続きは期限があるものとないものがあります。できるだけ速やかに行いましょう。相続放棄は3カ月以内、被相続人の確定申告(準確定申告)は4カ月以内、相続税の申告と納付、相続財産の登記と名義変更は10カ月以内になります。
Q,相続の手続きはしなくても大丈夫ですか?
A,相続登記をしないことですぐに問題が起きるわけではありません。しかし「祖父が亡くなった後に相続人である父が亡くなっ た」といったことが起きますと、相続人が増えて複雑化することがあります。会ったことがない人と相続の話をすることになり話がまとまらなくなることもあります。
Q,相続登記にはどんな書類が必要ですか?
A,手続きの内容により違います。以下は遺言書のない場合の一例です。
亡くなられた方
・生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本や改正原戸籍なども含みます)
・亡くなった時の最後の住所地がわかる住民票の除票又は戸籍の附表
相続される方
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続される方の住民票の写し(コピーではありません)
不動産の相続登記
・相続する不動産の登記簿謄本
・相続する不動産の固定資産評価証明書
その他
・相続人の間で話し合い、法定相続分とは違う相続登記をする場合は遺産分割協議書
・遺産分割協議書に添付する相続人全員の印鑑証明書
・司法書士への委任状
Q,必要な書類を集めるのが大変です。どうしたらいいでしょうか?
A,戸籍謄本など必要書類を全て集めるのは大変な作業になると思います。ご依頼いただければ当事務所で手続きいたします。