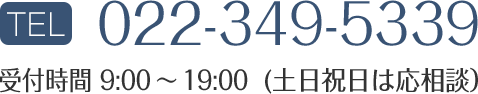遺産の分け方
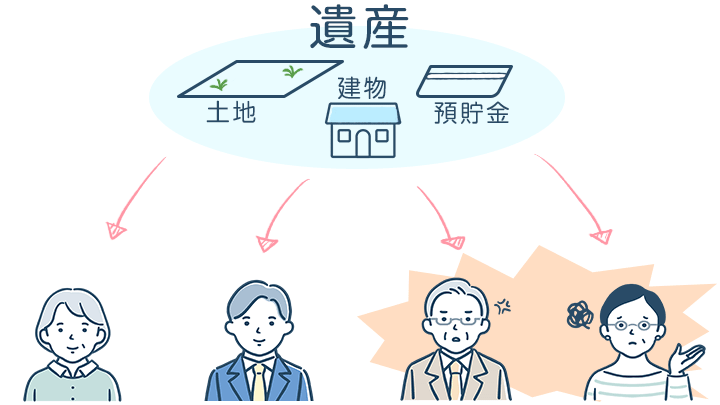
現物分割
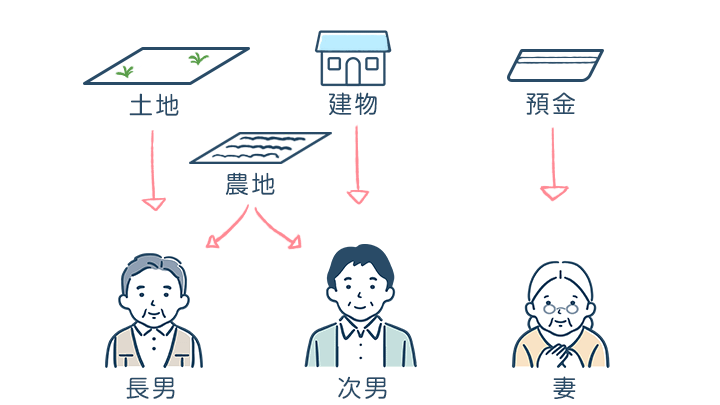
「土地は長男、建物は次男、預金は妻、農地は長男と次男が2分の1ずつ共有で」というように遺産をそのまま分割していくことを現物分割といいます。
現物分割は分かりやすく手続きも簡単で遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、遺産を公平に分けるのが難しいというデメリットもあります。現物分割と組み合わせて代償分割という方法があります。
代償分割
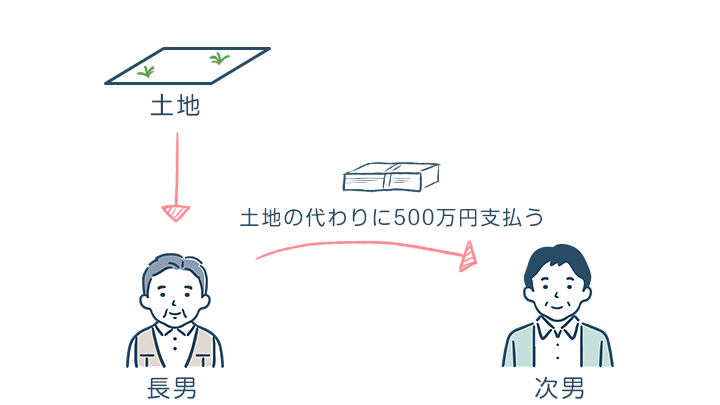
「土地を長男が取得する代わりに、長男は次男に500万円支払う」というように、ある相続人が遺産を多く取得する代わりに別の相続人にお金を払うという方法を代償分割といいます。
遺産を細分化せずにそのまま残せて公平に分けることができます。代償分割は金銭の支払い能力が必要です。現物分割も代償分割も難しい場合は換価分割という方法を考えましょう。
換価分割
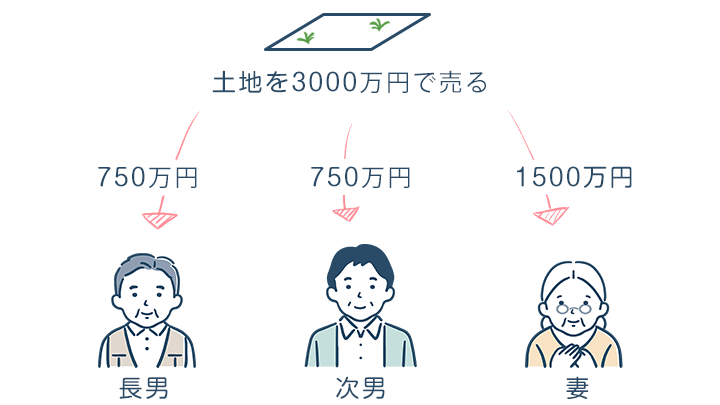
「土地を3000万円で売って、妻が1500万円を、長男と次男が750万円ずつ取得する」というように、遺産を売ってその代金を分配するという方法を換価分割といいます。
遺産を公平に分割することができますが現物を処分しなければならず、売却に手間と費用、譲渡所得税等の税金がかかるというデメリットもあります。
共有分割
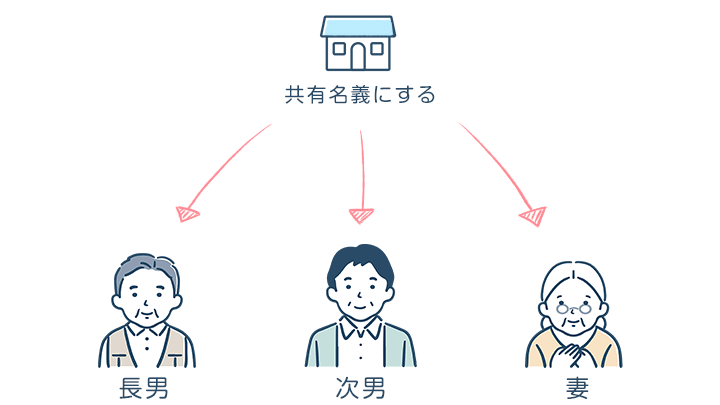
見た目には分割されていない一つの不動産ですが、その一部または全部を共有名義にするという方法が共有分割です。登記簿謄本には相続人それぞれの名前と持分が記載されます。
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書によって対外的に誰が何を相続したのかを主張できます。その反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され撤回する事ができません。万が一遺産分割協議書を書き換える場合には相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更をスムーズに進めることが可能となります。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、いくつか注意点があります。
1.遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。一人でも欠けていた場合には無効になります。戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
※ 全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
現実的には1通の遺産分割協議書の案を作成し、他の相続人にこの内容でよければ実印を押してもらう方法が取られます。
2.相続人が押す印鑑はできれば全員実印にしましょう。
遺産分割協議書の効力としては三文判でも有効ですが、実際の手続き上は法務局、銀行などほとんどが実印でないと受理してもらえません。
3.財産の表示方法に注意しましょう。不動産の場合は住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は支店名、口座番号まで書いてください。
4.遺産分割協議書が用紙1枚に収まらず複数枚にわたる場合は法定相続人全員の実印で契印にしてください。
※契印とは、文書が2枚以上にわたる場合に1つの文書であることを証明するために2枚の用紙にまたがって押す印のことをいいます。
全ページをホチキス等でとじ、ページを開いた部分にまたがるように押印します。全てのページとページを印鑑で繋ぐことにより1つの文書としての効力を有します。
法的な判断を必要とするケース
上記のほかに法的な判断を必要とするケースについて、よくある事例をご紹介します。
相続人に未成年者がいる
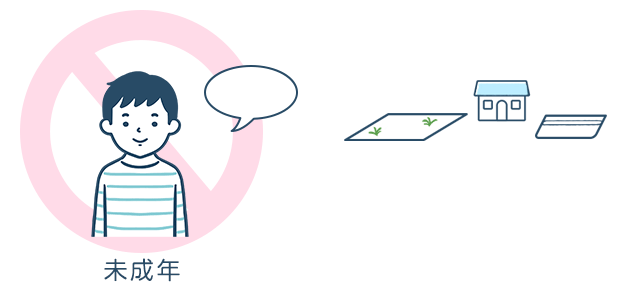
未成年者は遺産分割協議をすることができません。この場合、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
- 未成年者が成年に達するまで待つ
- 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
一般的には未成年者が重要な法的手続きをする場合、親が法定代理人となって法的手続きを行います。
しかし、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
<例>夫が死亡し、相続人が妻と子であるとき
このような場合、親と子供で遺産分割協議を行なうように感じますが、このときの親と子供は利益が相反することになり親は子供の代理人になる事が出来ません。
また、子供だけが相続人である場合であっても数人の子供を一人の親が代理をすることもできません。このようなときには未成年者ひとりひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人として祖父を選任するなどといった申し立てもできますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。実際の手続は特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出るときに遺産分割協議書(案)の添付が必要になります。
相続人に行方不明者がいる
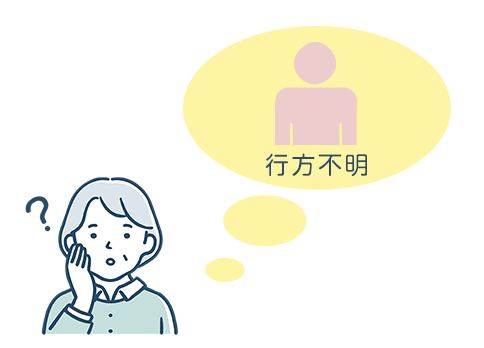
相続人の中に行方不明者がいる場合には2つの方法が考えられます。
- 失踪宣告されるのを待って遺産分割協議をする
- 不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、その財産管理人を交えて遺産分割協議をする
相続人に認知症で協議できない者がいる
一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。一時的にも意識が回復することがない場合には成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。